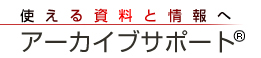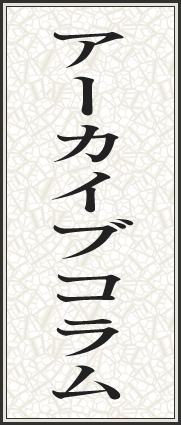使いやすくなった国立公文書館
東京・北の丸の一角に国立公文書館があります。先日、およそ一年ぶりに出向きましたが、サービスが格段に向上していて、関係者の努力、改革への熱意を感じました。
まず驚いたのは、持参のデジタルカメラでの資料撮影が自由化されたことです(一部に制限があります)。これまで、一部の県立や市立の公文書館等で、デジカメでの撮影を許可していましたが、「本丸」たる国立公文書館が自由化に踏み切ったことで、全国のアーカイブ機関も追随するものと思われます。
もうひとつは、「昼休み」がなくなって、閲覧室がオープンしている間は、いつでも資料の出納をしてくれるようになったことです。
かつては、国立国会図書館も昼休みの出納をしませんでしたが、いまやそのような「役所の常識」は罷り通らなくなっています。
また、一階ロビーでの企画展にも旺盛に取り組んでおり、なかでも終戦記念日を中心に展示された天皇の「終戦の詔書」の展示は、全国紙(読売新聞・8/23)でも紹介され、緊迫した状況を今に伝える「原本の力」に注目が集まりました。
国立公文書館は、その使命の重さに比べて、財政面でも組織面でも十分とは言えません。遠からぬうちに収蔵スペースも一杯になってしまうといいます。予算配分が十分でない一因は、利用者の少なさにあると言います。
平成24年度の閲覧者数は本館・つくば分館あわせて4,549人、少ないと言わざるを得ません。文書館は、少し前までは、「素人」には近づきがたい施設でした。
しかし、今では家庭や、閲覧室のパソコン端末から資料の検索、利用(閲覧)請求書の作成までできて、だれでも、ごく簡単に資料にアクセスできるようになりました。出てきた資料をデジカメでパチパチ撮れるなんて、少し前から見たら「夢」のような話です。
使いやすくなった国立公文書館、多彩な企画展も好評です。一人でも多くの人に足を運んでいただきたいと思います。その一歩が、アーカイブズの健全な発展に直結するのです。

ヘリテージサービス事業部アーカイブ担当 中川 洋
歴史系博物館学芸員として資料の収集・管理や展示・教育業務に携わり、現職に就く。
現在は、企業および学園アーカイブのコンサルティング、プランニング、マネジメントに従事。