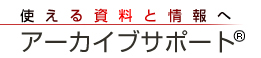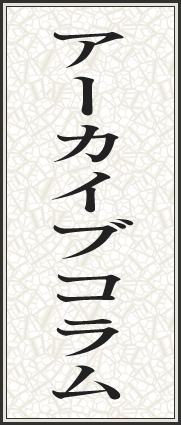- 01:アーカイブって何?
- 02:百花繚乱 - 工夫をこらす企業博物館
- 03:データ保存、ベストなメディアは?
- 04:公文書管理、法制化へ一歩踏み出す
- 05:公文書管理法の行方
- 06:地方公文書館の奮闘
- 07:水戸黄門のアーカイブズ
- 08:アーカイブ電子化の功罪
- 09:時を貫く記録
- 10:まずどこから手をつけるか
- 11:知られざる専門図書館―情報の宝庫
- 12:私的アーカイブズのすすめ
- 13:資料整理と目録
- 14:資料整理と目録の大事さ
- 15:将来に備えるデータ保存
- 16:電子化の仕様
- 17:企業史と史料館のこと
- 18:歴史的資料の分類と保管のヒント
- 19:写真の保管法
- 20:アーカイブは利益を生む
- 21:注目される地方自治体の歴史的公文書
- 22:一人の若者の死とアーカイブ
- 23:開港150年に沸くみなと横浜のアーカイブ
- 24:これからが正念場、記録管理の法律案
- 25:画像データの整理法
- 26:草の根アーカイブ
- 27:知的財産権とアーカイブ
- 28:捨てる整理、残す整理
- 29:新製品創出とアーカイブ
- 30:資料のための防災対策
- 31:受け継いできた職人の技が環境問題で蘇る
- 32:歴史的遺産の活用―観光と産業
- 33:観光資源は大きなアーカイブ資源
- 34:フロッピーディスクの終焉
- 35:文書の長期保存
- 36:「レコード」の原義
- 37:アーカイブ専門家の養成
- 38:資料の保存環境
- 39:ISO15489とは
- 40:シベリア抑留者のアーカイブ
- 41:地域史の再生産の場で
- 42:広島原爆の記録
- 43:電子メールの管理と保存
- 44:倉庫保管文書の整理
- 45:英国の企業アーカイブ紹介
- 46:学園アーカイブの時代
- 47:資料の劣化対策(紙・マイクロフィルム)
- 48:インターネットはアーカイブ出来ている?
- 49:博物館学芸員課程のアーキビスト教育
- 50:将来を切り拓くアーカイブ
- 51:記録を消し去れない仕組みづくり
- 52:名もなき人たちのアーカイブ
- 53:電子データの長期保存
- 54:記録と記憶
- 55:文書館に行きましょう
- 56:文書管理規程の見直しを
- 57:アーキビストの要請と養成
- 58:鎮魂のアーカイブ
- 59:個人資料の整理法(準備作業編)
- 60:アーキビストはレコード・マネジャーも兼任?
- 61:アーカイブの世界遺産
- 62:組織資料の整理法(整理作業の目標設定)
- 63:「文書」と「記録」
- 64:教育への情熱の証
- 65:アーカイブ、その作業手順について
- 66:デジタルデータのバックアップ
- 67:三菱一号館美術館の開館
- 68:アーカイブの作業手順 リサーチとプランニング
- 69:ファイルの活用
- 70:ターンドデジタル、ボーンデジタルのこと
- 71:外務省の英断
- 72:「電子記録マネジメントコンソーシアム」の発足
- 73:6月9日「国際アーカイブズの日」
- 74:成功するアーカイブズ構築のポイント
- 75:7月9日「大学の歴史を伝えるもの」
- 76:明治の地図で探る戦国の城
- 77:電子メールの恐ろしさ
- 78:8月20日「流出文化財をめぐって」
- 79:奈良時代の公文書管理
- 80:CSR(企業の社会的責任)が ISOに
- 81:タブーなき情報公開を
- 82:平安時代のアーカイブズ
- 83:ペーパーレス・オフィスは実現するのか
- 84:モノをして語らしめる
- 85:武士の戦いと文書
- 86:書評「日本の公文書」
- 87:2010年を振り返って
- 88:甲斐源氏系図と文書作成認識
- 89:二つの情報流出事件から
- 90:フェイスブックとアメリカ国立公文書館
- 91:災害に強いアーカイブ構築を
- 92:災害と記録
- 93:情報公開法の改正
- 94:命を守るアーカイブ
- 95:歴史資料ネットワークの保全活動
- 96:平安貴族にとっての記録
- 97:ビジネス・アーカイブズの国際シンポジウム
- 98:炭鉱労働者の絵画が世界記憶遺産に登録
- 99:知的生産のためのアーカイブ
- 100:日本アーカイブズ学会の
アーキビスト資格認定制度 - 101:九電の「やらせメール」事件をめぐって
- 102:記録と通信の技術革新
- 103:映像資料の保存(1)―フィルムの危うさ
- 104:日本のアーカイブズの問題点(1)
- 105:アナログ写真の整理
- 106:日本のアーカイブズの問題点(2)
- 107:映像資料の保存(2)―デジタル化する前に
- 108:資料の保存環境
- 109:なんのための分類か 図書と史資料の分類
- 110:米国国立公文書館 訪問記
- 111:音源の電子化
- 112:組織内で発生する『メモ』は公文書か否か
- 113:カナダ国立図書館・公文書館 訪問記
- 114:映像の電子化
- 115:『公文書をつかう』を読んで考えたこと
- 116:原子力災害対策本部の議事録問題
- 117:資料の保存と公開
- 118:メタデータなくしてデジタルアーカイブなし
- 119:資生堂企業資料館見学記
- 120:家庭のアーカイブからの発見
- 121:脳を創るアーカイブ―『脳を創る読書』より
- 122:電子文書に頼らない文書管理?―統計解析を用いたメタデータ管理
- 123:アーキビストの眼:電子記録の性質(1)
- 124:アーキビストの眼:電子記録の性質(2)
- 125:アーキビストの眼:電子記録の性質(3)
- 126:アーキビストの眼:電子記録の性質(4)
- 127:デジタル記録の信頼性確保 ―インターパレスの成果―(1)
- 128:東電の会議映像の公開と企業の情報開示
- 129:消え行く紙媒体-大学の現場から
- 130:アーキビストの眼:“アーカイブする”?
- 131:デジタル記録の信頼性確保―インターパレスの成果―(2)
- 132:研究関係記録のアーカイブ―山中教授のノーベル賞受賞から
- 133:シュタージ(Stasi)文書の復旧:「世界最大のジグソーパズル」
- 134:その後の震災関連アーカイブ
- 135:Web上のデータベースを探索してみましょう―まずは情報の掘り起こしから
- 136:アーキビストの眼:『archives(アーカイブズ)』の定義の変化
- 137:映像フィルムの保存をめぐって
- 138:アーキビストの眼:『archives(アーカイブズ)』の定義の変化(2)
- 139:福岡共同公文書館の開館
- 140:オフィスの移転は、文書管理見直しのチャンス
- 141:アーキビストの眼:保存か活用か
- 142:よみがえった姫路モノレール
- 143:二つの企業ミュージアム
- 144:進化/深化するデジタルアーカイブ
- 145:定期刊行物のアーカイブズ
- 146:アーキビストの眼:企業アーカイブズ、再考
- 147:記録管理・アーカイブズの専門職問題
- 148:磁気テープのデータ保存で安心?
- 149:今、活かされる江戸時代のアーカイブ
- 150:アーキビストの眼:『残す』=『選ぶ』
- 151:MLA連携よりRMA連携を
- 152:写真の整理をいつやる?今でしょ
- 153:使いやすくなった国立公文書館
- 154:記憶の記録とオーラルヒストリーの『recordness(記録性)』
- 155:「宇土市の文書管理」
- 156:残る記録・残らない記録・残す記録
- 157:一枚の史料から見える歴史の実像
- 158:企業記録と地方自治体アーカイブズ
- 159:松本市文書館訪問記
- 160:特定秘密保護法の成立と海外事例の論考から見る課題
- 161:地方公文書館の奮闘
- 162:廃棄と保存~ジョン・レノンに関する記録文書から学ぶ~
- 163:「良い記録の要件とは?」
- 164:バチカンから愛をこめて―近世豊後のキリシタン文書の発見
- 165:古文書を読む
- 166:ネガフィルムの保存について、再考
- 167:社史もアーカイブも大切です―企業の歴史・資料を継承するために―
- 168:モノ資料の魅力
- 169:無形文化財のアーカイブ化
- 170:展示室にない資料を見るためには
- 171:土木学会が「土木コレクション」を巡回展示
- 172:日本の文字と記録
- 173:土地の記憶-地図というアーカイブ
- 174:「アーカイブ」の意味
- 175:アーカイブズとPreventive Csonservation
- 176:映画の復元と保存に関するワークショップ
- 177:MLAの学び―アーカイブ作業への応用―
- 178:「におい」のアーカイブ
- 179:地方公文書館と専門職
- 180:米国アーキビストの実態
- 181:記憶の継承とアーカイブ
- 182:世界記憶遺産とアーカイブ
- 183:「情報ガバナンス」という考え方
- 184:スター・ウォーズの世界のアーカイブズ
- 185:戦争と平和を語り継ぐ
- 186:分類を考える 1 ~形態別分類と種類による分類~
- 187:武田晴人先生の講演を聴いて
- 188:災害と資料
- 189:WEBでの公開がすすむデジタルアーカイブズ
- 190:分類を考える ~内容分類~
- 191:日本人の言語感覚と記録
- 192:記録媒体と再生機器
- 193:身近にある「遺産」
- 194:国立公文書館長がビジネス・アーカイブズを語る!!
- 195:社史とアーカイブズ
- 196:資料整理のタイミング
- 197:統計資料の活用-『日本帝国統計年鑑』を事例として-
- 198:大学キャンパスの歴史遺産
- 199:分類の変遷3 ISAD(G)(国際標準:記録史料記述の一般原則)を援用した分類方法について
- 200:学芸員は“がん”か?
- 201:資料の保管場所-どこに、何を、どれくらい-
- 202:図書館の新しい試み デジタルアーカイブズの公開
- 203:日米ビジネスアーカイブセミナーを開催します
- 204:資料整理を考えられている方だけでなく、広報ご担当者の方も必見です! ~日米ビジネス・アーカイブセミナー開催のお知らせ~
- 205:10月24日東京・27日大阪で『学園アーカイブセミナー』を開催します
- 206:神戸製鋼の検査データ改ざん
- 207:資料整理とデジタル化
- 208:『南満洲鉄道株式会社』の記録管理
- 209:成田空港問題のアーカイブズ
- 210:国立公文書館「アーキビストの職務基準書」(2017年12月版)を読んで
- 211:老舗とは何か
- 212:「まず電子化!」で大丈夫??
- 213:デジタルアーカイブの二次利用
- 214:活用可能な目録作りをめざして
- 215:2018年度アーカイブセミナーを開催します
- 216:企業アーカイブ構築を成功させるために
- 217:1000年続くアーカイブズ
- 218:くずし字を読む
- 219:明治時代の記録管理から考えたこと
- 220:2018年度アーカイブセミナー(関西地区)を開催します
- 221:「アーキビストの職務基準書」とアーキビスト認証への期待
- 222:森友問題その後―検察審査会が「不起訴不当」を議決
- 223:アーカイブズの活用実績をアピールするには
- 224:“その時”ではもう遅い できることからコツコツと
- 225:年史編纂前のアーカイブについて
- 226:バチカン文書館と資料公開
- 227:日系企業の記録編纂-「兼松商店」を事例として
- 228:『社史・アーカイブ総研の挑戦-組織の歴史継承を考える-』を刊行しました
- 229:公文書管理をめぐる課題
- 230:日本人の議論下手という特性について
- 231:アーカイブズの肖像権ガイドライン
- 232:社史制作とアーキビストの役割
- 233:デジタルアーカイブの現状と展望
- 234:新型コロナとアーカイブ
- 235:新型コロナとアーカイブ II
- 236:アーキビスト認証制度の開始
- 237:デジタル庁設置とアーカイブ
- 238:アーカイブとクラウドファンディング
- 239:センシティブ情報とアーカイブズ